相続は新潟の税理士に相談。相続税申告、相続節税対策、遺言、相続手続き承ります。相続税申告や手続きは税理士にご相談ください。
営業 時間 | 平日 9:00~17:30 ※夜間は要予約 |
|---|
生前贈与のやり方
メリットデメリットを解説
相続税が増税の方向に進んでいることで、「相続税対策」を行う方が増えてきています。
相続税対策の代表的な手法の一つである生前贈与ですが、要件を満たしていない場合、あとで無効と判断されることもあります。
また、贈与をする際にかかる贈与税は相続税よりも税率が高いため、活用方法を間違えてしまうと普通に相続をしたときよりも遺族の方の税負担が高くなってしまう可能性があります。
無駄な税金を払わないためにも、正しい方法で確実に贈与を行いましょう。
生前贈与とは
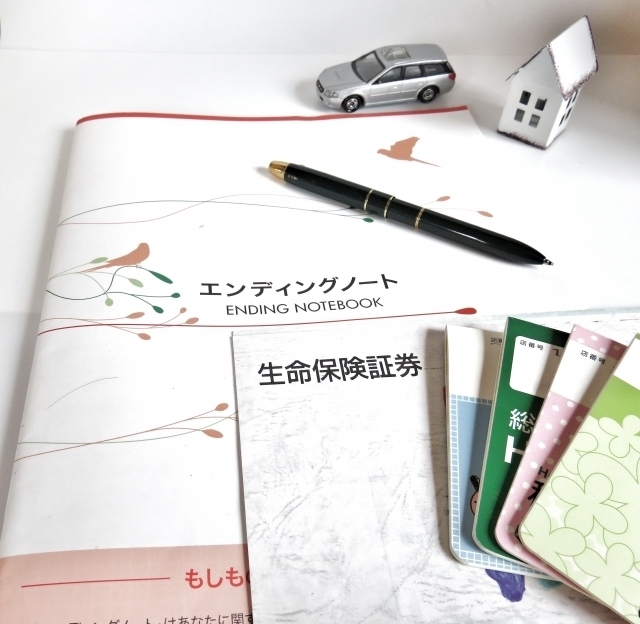
まず「贈与」とは、一般的に自己(贈与者)の財産を無償で相手(受贈者)に与えることをいいます。
贈与者、受贈者相互に「あげる」「もらう」という意思表示があることが大前提となります。
このうち「生前贈与」とは、相続対策を目的として贈与者が生前に贈与者の推定相続人である子や孫へ財産の贈与を行うことをいいます。
口約束でも贈与を行うことはできますが、贈与者が死亡時にスムーズに相続を行うためにも、契約書の作成をお勧めします。
贈与者の推定相続人である子や孫へ贈与を行った場合、受け取った側に「贈与税」が発生します。生活費や養育費等の援助として消費したお金などには贈与税はかかりませんが、消費されていない場合は贈与税の対象となります。
また、受贈者が把握、管理していない口座名義に財産を移転させたものも、名義預金となり贈与と認められず、贈与者本人の財産とみなされ相続税の対象となります。
詳しくは国税庁HPにてご確認ください。
≫贈与税(国税庁)
効果的な生前贈与のポイント
- 贈与の制度(課税制度・非課税枠)を理解すること
- 節税効果の高い贈与を行うこと
- 注意事項を把握し、事前にしっかり検討すること
贈与税の計算方法
{ その年分の贈与財産の合計額 - 基礎控除額(110万円) } × 贈与税率 = 納付税額
贈与税の課税制度
贈与が行われた際の贈与税の課税制度には、「暦年課税」と「相続時精算課税」があり、贈与を受けた側に申告義務・納税義務が生じます。
贈与が行われた場合、その翌年の2月1日から3月15日までに贈与税の申告・納税を行います。
暦年課税
暦年課税は、その年の1月1日から12月31日までに贈与された財産の合計額に応じて課税される方式のことです。
ただし、贈与税には1人当たり年間110万円の基礎控除(税金がかからないライン)が認められているため、贈与者と受贈者の関係を問わずにある1人が受け取った財産の合計が110万円以下であれば申告も納税も不要です。
それ以上の贈与がある場合は、110万円を超えた部分に対してのみ贈与税がかかります。
『暦年贈与』はこの仕組みを利用した相続対策で、上手に活用することで
- 一人の推定相続人に対して長期間かけて財産を無税で贈与することが出来る
- 複数の推定相続人に対して一年間のうちに数百万円を無税で贈与することが出来る
といった贈与が可能になります。
※生前贈与加算:贈与者の相続開始前3年以内に贈与された財産については、相続税の対象となるので覚えておきましょう。
暦年贈与するときの注意点
- 定期贈与としてみなされないこと
- 相続開始前三年以内の贈与に注意すること
- 名義預金に該当しないよう注意すること
相続時精算課税
相続税精算課税制度とは、贈与者が60歳以上の親または祖父母かつ、受贈者が贈与者の推定相続人である20歳以上(令和4年4月1日以後の贈与については18歳以上)の子または孫の場合に、最大2,500万円に達するまでは贈与税がかからない制度です。
(※2,500万円を超えた分は20%の贈与税が課せられます。)
贈与財産の種類、金額、贈与回数、年数に制限はありません。
例えば「一括で多額の財産を贈与したい」といった場合は、こちらの制度を活用することで納税義務を先送りすることが出来ます。
ここでポイントになるのが、あくまで納税義務を「先送り」にしているという点です。相続が発生した段階で先に贈与を受けていた財産に対して「相続税」が掛かるため、納税義務は残っているという点にご注意ください。
相続時精算課税制度の注意点
- 贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間に一定の書類を添付した贈与税の申告書を提出する必要あり
- 一度選択したら暦年課税に戻すことはできない
- 相続時に相続財産に含まれ、相続税が発生する
生前贈与の代表的な非課税特例
生前贈与には、2つの課税制度の他に、以下の非課税特例が設けられています。
これらは、暦年課税・相続時精算課税との併用が可能であり、うまく活用できれば大きな節税効果が得られます。
ただし、期間限定のものもあり、早い段階で専門家へ相談されることをおすすめいたします。
夫婦間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例。
ちなみに、夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後の贈与が対象となります。
詳細は以下の国税庁HPにてご確認ください。
住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税枠
令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己(18歳以上(令和4年3月31日以前の贈与については20歳以上))の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得または増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合において、一定の要件を満たす場合に、非課税限度額(省エネ等住宅の場合には1,000万円まで、それ以外の住宅の場合には500万円まで)の金額について、贈与税が非課税となります。
※住宅ローンの支払い、土地だけの購入には使えません
教育資金贈与(教育資金一括贈与)
令和5年3月31日まで延長が決定されたこの特例は、直系尊属からの「教育資金の贈与」として、受贈者(子供や孫など)1人につき総額1,500万円まで非課税になるというものです。
(学校等以外、例えば塾や習い事等への支出は500万が上限)
原則として、受贈者が満30歳に達した場合や口座残高が0になった場合などに終了し、口座残高がある場合はその残高分に対して贈与税が課税されます。
結婚・子育て資金贈与の特例
正式名称「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」は、令和3年の税制改正で令和5年3月31日まで延長が決まりました。
子供や孫のために、父母や祖父母が20歳以上(令和4年4月1日以後の贈与については18歳以上)50歳未満の子や孫のために結婚や出産または育児に要する資金を渡す贈与について、1,000万円まで贈与税が非課税になる制度です。
このうち結婚費用に充てられるのは300万円までであり、「結婚」の費用には婚礼、披露宴費用、新居の住居費など、また「子育て」の費用には不妊治療費、妊娠中の通院費、子どもの医療費、保育料などが該当します。
贈与の節税効果を高めるには
生前贈与は相続税対策の代表的な手法であり、実際に贈与で節税をするというのは、以下の関係が成り立つことを言います。
贈与により減少する相続税額 > 贈与を行うことにより支払う贈与税額
この関係を成り立たせるために、①相続財産の把握と相続税の概算を試算し、②相続税の税率を把握、③相続税の税率(増減割合)を下回る贈与金額を決定しましょう。
相続税対策(特に生前贈与)は計画的に行うことでより節税効果が高まります。
「こんなはずじゃなかった」とならないために、より早く、的確に対策を講じましょう。
<贈与を利用した相続税対策例>
- 小規模な贈与を繰り返し行い、相続財産を減らす
金額の僅少な贈与は、節税効果は小さいですが継続的に長期間行うことで総合的な節税効果は大きなものになります(連年贈与)
※暦年課税による贈与を行う場合はこの方法に該当しますが、明らかな連年贈与は「定期金に関する権利の贈与」として贈与税の対象となる可能性があるので注意しましょう。
- 時価より相続税評価額が低い財産の贈与を行う
贈与財産の評価額は相続税評価額となるため、時価より相続税評価額が低い財産の贈与は節税効果が高いといえます。
- 値上がりする財産の贈与を行う
将来価値の上昇する財産は継続して保有するほど相続税も増加するため、評価額の低いうちに贈与を行うことで相続財産の増加を防ぐ効果があります。
贈与を行う際の注意点
- 「贈与契約書」を作成し、双方の意思を書面に残すこと
- 贈与は受け取った側が自由に使える状態である必要があるため、通帳や印鑑は贈与を受けた本人が管理する
- 多額の贈与を行った場合、受け取った側で多額の納税が生じるため、納税資金を考慮して贈与を行う
- 連年贈与をする場合は自己判断せず、専門家に相談する
- 相続開始3年以内の贈与は相続税の課税対象となるため、贈与を行う場合は早い段階から計画的に行う
参考:2時間でわかる はじめての「相続税・贈与税」入門 森山貴弘著
不動産の贈与は登記が必要!
贈与財産が不動産の場合は「登記」が必要です。
登記が行われていない場合、贈与はないものとみなされてしまいます。
不動産の贈与では、「登録免許税」「不動産取得税」と「登記費用」がかかります。
- 登録免許税
原則、固定資産税評価額の合計×税率2%で計算し、登記申請時に納付する。
- 不動産取得税
原則、固定資産税評価額×税率3%で計算し、不動産取得時に課税となる。
都道府県の税金のため、都道府県から課税の通知が来る。
- 登記費用
登記手続きを司法書士に依頼する場合に、司法書士へ支払う報酬。
不動産の生前贈与を行う場合には贈与契約書を作成し、印紙を貼る。
生前贈与を上手く活用するために

生前贈与は、相続税対策の中で代表的な手法であり、上手く活用できればその節税効果はとても大きなものになります。
しかし、しっかり計画を立てて行わなければ、せっかく行った対策が無効となり、さらに本来払わなくてよい税金を払うことになってしまいます。
生前贈与をはじめ相続は全体像をしっかり把握し、計画的に進めることが成功へとつながります。
親族へ少しでも多くの財産を残したいとお考えの方は、まずは一度専門家へ相談することをおすすめいたします。
私どもは、豊富な経験とノウハウを基に、「ご家族にとって一番よい形」を提案させていただき、お客様に寄り添いサポートさせていただきます。
まずは、当協会の無料相談をぜひご活用ください。
ご依頼されるかどうかは、お客様の自由です。相談したからといって必ず依頼しなければいけないということはありませんので、安心してご相談下さい。
新潟の相続専門の税理士が、お客様の不安を解消し、最適なアドバイスとサポートをさせていただきます!
新潟市、三条市、その他新潟県内の方は、お気軽にご相談ください。
税理士への相続税・贈与のご相談はこちら

お気軽にご相談ください!
お約束1:感じの良い対応
お約束2:勧誘はいたしません
税理士・著書のご紹介(共著)

新潟相続協会 概要
新潟相続協会
(L&Bヨシダ税理士法人)
ご連絡先
◆新潟 相続オフィス
新潟県新潟市中央区女池4-18-18マクスウェル女池2F
☎025-383-8868
◆三条 相続オフィス
新潟県三条市東裏館2-14-15
☎0256-32-5002
対応地域
新潟県内全域対応
新潟県新潟市中央区、新潟市西区、新潟市東区、新潟市北区、新潟市江南区、新潟市西蒲区、新潟市南区、新潟市秋葉区、長岡市、三条市、見附市、加茂市、小千谷市、新発田市、村上市、柏崎市、上越市、胎内市、糸魚川市、弥彦村、燕市、五泉市、燕三条地域
その他県内全域対応












