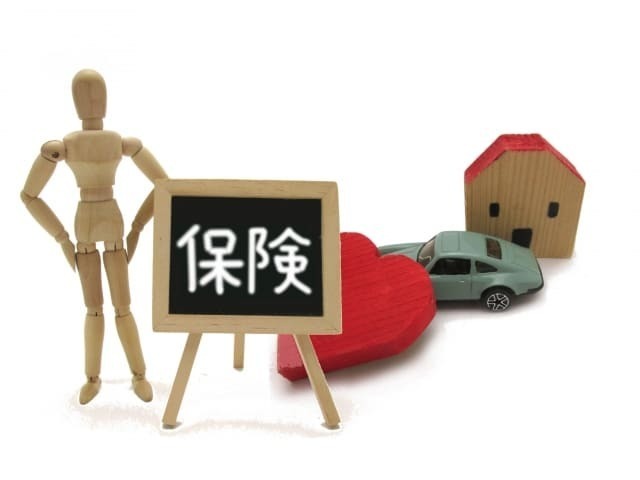相続は新潟の税理士に相談。相続税申告、相続節税対策、遺言、相続手続き承ります。相続税申告や手続きは税理士にご相談ください。
営業 時間 | 平日 9:00~17:30 ※夜間は要予約 |
|---|
亡くなった方の生命保険を確認する方法
亡くなった方(故人または被相続人)が生命保険に加入していた場合、その種類によっては死亡保険金を受け取ることが可能です。
しかし、死亡保険金の請求には期限があるため、葬儀などが一通り落ち着いたらなるべく早く保険会社に請求するようにしましょう。
被相続人が生前に働いていた会社で加入しているものもあるかもしれないので、勤務先への確認もお忘れなく。
この記事では、亡くなった方の生命保険の確認方法についてご紹介いたします。
亡くなった方(被相続人)の生命保険を確認する方法
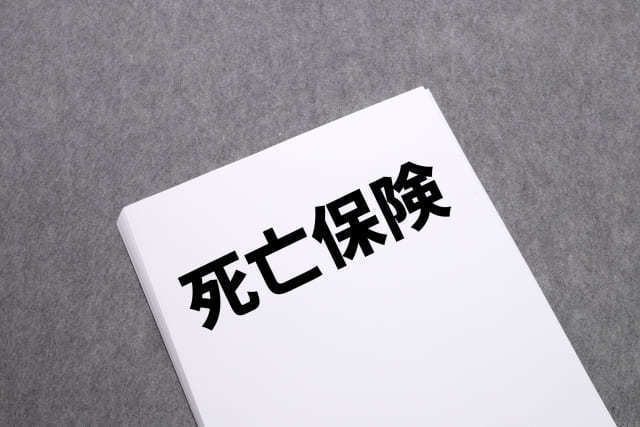
亡くなった方(以後、被相続人と言います。)が加入していた生命保険から支払われる死亡保険金は、法律上は原則として相続財産には含まれません。
しかし相続税を算出する際に「みなし相続財産」として含まれることになります。
ちなみに死亡保険金は、相続人等が自主的に加入していた保険会社に請求しなければ受け取ることができません。
また、死亡保険金の請求には期限があり、その多くが被保険者が亡くなった日から3年以内で時効となってしまいます。
被保険者(被相続人)が生命保険に加入していることを家族・親族に知らせずに亡くなった場合は気づくことが難しいため、受け取らないうちに時効となってしまう可能性が高いです。
そのため、被相続人が生命保険に入っているかどうか分からない場合は以下の方法で調べてみましょう。
- 保険証券を確認する
- 郵便物を確認する(『ご契約内容のお知らせ』や『生命保険料控除証明書』)
- 通帳を確認する
- パソコンやスマホを確認する
- クレジットカード明細を確認する
- 会社に問い合わせる
- 一般社団法人生命保険協会で調査する
それぞれ詳しく説明いたします。
保険証券を確認する
被相続人が加入していた生命保険を知るためには、まず第一に「保険証券」を確認しましょう。
保険証券は保険契約が成立したことの証明であり、契約成立後に必ず保険会社から保険契約者宛に交付される書類です。
保険証券には「証券番号」「契約者名」「被保険者名」「受取人名」「保険料」「給付金」「保険期間」などの契約内容がすべて記載されています。
もし保険証券に詳しい内容が記載されていない場合には、証券番号等を控えた上で保険会社へ問い合わせてみましょう。
被相続人宛の郵便物を確認する
生命保険に加入している場合、「ご契約内容のお知らせ」が届いている可能性があります。
主に誕生月や契約月に応じて交付されます。
また、確定申告に向けて10月以降に「生命保険料控除証明書」が届くため、これらの種類がある場合はなにかしらの保険に加入していると考えられます。
書類の内容を確認し、送付元の保険会社へ問い合わせましょう。
書類を探す場合には、タンスやデスクの中、バッグや普段なら探さない場所も細かく探していくことが大切です。
通帳を確認する
「保険証券」や「ご契約内容のお知らせ」等の書類が見つからない場合は、本人名義の金融機関の通帳を確認してみましょう。
保険料の支払いを口座振替にしている場合は、通帳に記載されている履歴から保険会社を特定することが可能です。
パソコンやスマホを確認する
被相続人の加入していた保険会社がネット保険の場合には、取引明細はオンラインですべて確認できるため郵便物が届かない可能性があります。
その場合は、亡くなった方の利用していたパソコンやスマホの「ブックマーク(お気に入り)」や「閲覧履歴」などを確認してみましょう。
保険会社のサイトやログイン画面が登録されている場合は、その保険会社を利用している可能性が高いでしょう。
また、メールの送受信履歴から確認できることもあります。
クレジットカード明細を確認する
保険料の支払いをクレジットカードにしている場合は、クレジットカードの支払い履歴から確認できる可能性があります。
書類が届いていない場合はネットで確認してみましょう。
会社に問い合わせる
亡くなった方が会社員だった場合は、勤務先に問い合わせることで加入していたことが判明することがあります。
特に、団体で加入しているものは本人も加入していること自体を忘れてしまっているケースがあるため、年末調整時に提出する保険料控除申告書に記載がある場合などは勤務先の保険事務担当者に問い合わせてみましょう。
会社が団体として加入している場合は給与から天引きされている可能性もあるため、給与明細も確認しましょう。
死亡保険金を受け取る流れ
亡くなった方の死亡保険金は以下の流れで受取ることができます。
1.生命保険会社に連絡する
「保険契約者」または「保険金受取人」が被相続人が加入していた保険会社に口頭や書面等で連絡をしましょう。
2.死亡保険金の請求に必要な書類を揃える
保険会社からの案内に従い、請求に必要な書類を揃えましょう。
- 保険証券
- 死亡保険金の請求書
- 医師の死亡診断書または死体検案書
- 被保険者の住民票
- 受取人の戸籍抄本
- 受取人の印鑑証明 等
3.死亡保険金の請求手続きをする
請求に必要な書類が一通り揃ったら、受取人が保険会社に請求手続きを行います。
保険金の受取人がすでに亡くなっている場合は・・・
もし、生命保険の契約で指定されている受取人がすでに亡くなってしまっている場合は、誰が受け取ることができるのでしょうか?
答えは、「受取人の相続人」となります。
ここで注意して欲しいのが、被保険者の相続人が受け取るわけではないということです。
少し分かりづらいので例を挙げてご説明しますね。
例えば、母、兄(既婚者)、姉、妹という4人家族で
母が契約者・被保険者、兄が受取人の保険契約の場合
通常、母が亡くなった際の死亡保険金は兄が受け取ります。
しかし兄がすでに他界している場合は、兄の相続人である兄の妻と子供が死亡保険金を受け取ることになります。
母の保険契約ですが、母の相続人である姉と妹が受け取るわけではないということを覚えておきましょう。
また、兄の相続人が複数人いる場合には単純に頭割りで計算して受け取ることとなります。
死亡保険金の相続(遺産分割)
この記事のはじめで、「死亡保険金は法律上は原則、相続財産に含まれない」とお伝えしました。
基本的に生命保険の死亡保険金は、受取人指定されていれば受取人固有の財産として扱われます。受取人が相続人の一人であっても、遺産分割の対象とはなりません。
つまり、遺産分割協議書への記載が不要ということです。
そしてもし受取人に指定されている相続人が相続放棄をした場合にも、死亡保険金を受け取ることが可能です。
しかし、死亡保険金は相続税を算出する場合に「みなし相続財産」として含まれることになる、ともお話しました。
相続税の算出をする際には、「500万円×法定相続人の数」が非課税限度額となり、それを超える分が他の相続財産と合算され課税対象となります。
また、もし相続人の中に特別多くの利益を受ける方がいる場合には、他の人との不公平をなくすための「特別受益」という制度もあります。この制度については今は詳しく説明しませんが、保険の契約内容によっては贈与税や所得税の課税対象となる場合もあります。
死亡保険金の扱いについて、ご自身で判断が難しい場合には、税理士等の専門家へ相談することをおすすめします。
相続が発生するということは、親しい方が亡くなったということ。悲しみの中で相続争いに対応するのはとても辛いことです。
ささいなことでも大丈夫です。「相続について相談できる人が欲しい」という方は、まずはお気軽に当協会の無料相談をご活用ください。
まとめ
被保険者が生命保険に加入しているかどうかは、
- 保険証書を確認する
- 郵便物を確認する(ご契約内容のお知らせや生命保険料控除証明書)
- 通帳を確認する
- パソコンやスマホを確認する
- クレジットカード明細を確認する
- 会社に問い合わせる
- 一般社団法人生命保険協会で調査する
などの方法で調べることができます。
死亡保険金の請求できる生命保険の多くは、被保険者が亡くなった日から3年以内で時効となるため、忘れずに請求するようにしましょう。
もし期限が過ぎていた場合にも、問い合わせることで対応してもらえたというケースがあるので、諦めずに請求してみてくださいね。
※以上は本記事を作成時点の情報に基づいております。現在の内容と異なる場合があることをご容赦ください。
税理士への相続税・贈与のご相談はこちら

お気軽にご相談ください!
お約束1:感じの良い対応
お約束2:勧誘はいたしません
税理士・著書のご紹介(共著)

新潟相続協会 概要
新潟相続協会
(L&Bヨシダ税理士法人)
ご連絡先
◆新潟 相続オフィス
新潟県新潟市中央区女池4-18-18マクスウェル女池2F
☎025-383-8868
◆三条 相続オフィス
新潟県三条市東裏館2-14-15
☎0256-32-5002
対応地域
新潟県内全域対応
新潟県新潟市中央区、新潟市西区、新潟市東区、新潟市北区、新潟市江南区、新潟市西蒲区、新潟市南区、新潟市秋葉区、長岡市、三条市、見附市、加茂市、小千谷市、新発田市、村上市、柏崎市、上越市、胎内市、糸魚川市、弥彦村、燕市、五泉市、燕三条地域
その他県内全域対応