相続は新潟の税理士に相談。相続税申告、相続節税対策、遺言、相続手続き承ります。相続税申告や手続きは税理士にご相談ください。
営業 時間 | 平日 9:00~17:30 ※夜間は要予約 |
|---|
亡くなった方の所持する株式を確認する方法
亡くなった方(被相続人)が株取引をしていたことは知っているけれど、何の株を持っていたのか、どこの証券会社で取引していたかなど詳細については何も知らされていないというご家族は案外多いです。
しかし、もし突然当人が亡くなってしまった場合、ご家族はどのように確認したら良いのかが分からず困ってしまjうため、できるなら事前にご家族と情報を共有しておきましょう。
この記事では、生前に共有されないまま亡くなった方の所持していた株式を確認する方法についてご紹介いたします。
亡くなった方(被相続人)の株式を確認する方法

被相続人(故人)が株取引を行っていた場合、株式も相続の対象となります。
そのため、どこの会社の株式が何株あるのかを確認する必要があります。
一言で「株」と言っても現在は多種多様な株式があるので注意しましょう。
基本的に、所有している株式を確認するには
・証券会社へ問い合わせる
・通帳を確認する
・パソコンを確認する
・確定申告の控えを確認する
などの方法を試してみましょう。
証券会社へ問い合わせる
故人が株式を保有していたか調べる代表的な方法は、故人名義の口座がある証券会社(上場株式等の場合)や株式発行会社(非上場株式の場合)に問い合わせることです。
株取引を行っている場合はその証券会社からの郵便物が届いている可能性があります。証券会社は電子交付の場合を除き、年に1回以上「年間取引報告書」を郵送してきているはずです
もし郵便物がある場合は、記載されている連絡先を頼りに連絡してみましょう。
口座名義人が亡くなったや相続の手続きを行いたいと伝えれば必要な書類を送ってくれますし、相続人であることが証明されれば株の保有状況や預り金の残高などの情報を開示してくれます。
問い合わせの方法は電話やメール等色々な方法がありますが、一番簡単な方法は直接証券会社に出向いて確認することです。
訪問時は、本人確認に必要な書類や印鑑などを持参しましょう。
また、事前に証券会社の担当者と日程調整を行い、その際に当日用意しておくべき必要な書類なども確認しておくと手続きがスムーズに進みます。
必要な書類は本人か相続人かそれ以外の方かで内容が異なります。
ほとんどの証券会社のホームページには、よくある質問がQ&A方式で用意されており、その中には株式の保有者が亡くなった場合の対処法も記載されている場合があります。
その証券会社の対応を確認した上で問い合わせるようにしましょう。
また、中には証券会社ではなく信託銀行に特別口座がある場合もあるので、財産漏れにならないようによく確認するようにしましょう。
通帳を確認する
株式を保有している場合、通帳に「配当金」が振り込まれている可能性があります。
亡くなった方の通帳を確認し、心当たりのない振込はないか確認してみましょう。
パソコンやスマホを確認する
インターネットで株取引を行っている場合、明細はオンラインで確認できるため郵便物が届かない可能性もあります。
その場合、故人の利用していたパソコンやスマホの「ブックマーク(お気に入り)」や閲覧履歴などを確認してみましょう。
証券会社のHPやログイン画面が登録されている場合はその証券会社を利用している可能性が高いです。
また、パソコンのメールでも確認できることがあります。
どうしても証券会社が分からない場合は…
株式の相続で注意すべきこと
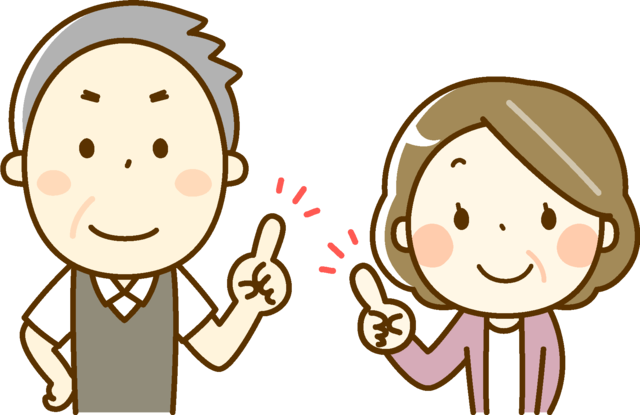
被相続人の所有していた株式を相続する際は、
・自身が相続人であることを確認する
・証券会社へのログインは個人利用のパソコンから行う
などの点に注意しましょう。
それぞれ詳しくご説明いたします。
自身が相続人であることを確認する
株式に限った話ではありませんが、そもそも相続人でなければ財産を相続することはできません。
相続人であることが確認できたら、「本人であること」「亡くなった方と血縁関係にあること」を証明しなければなりません。
公的書類で証明できない場合、財産を相続できない事態になりかねないので、まず第一に確認するようにしましょう。
戸籍上の血縁関係にあれば、市町村役場やコンビニ等で戸籍謄本を取得できます。
これらの確認を経て無事に相続人として株式を相続できるようになったら、亡くなった方の所有していた株式の手続きを行いましょう。
証券会社へのログインは個人利用のパソコンから行う
亡くなった方の株式を確認するために、証券会社の管理アカウントにログインする必要があります。
この際、故人が利用していたパソコンを使用するようにしましょう。
その理由は、セキュリティ上のロックがかかってしまうリスクを回避するためです。
証券会社のサイトによってはブラウザのクッキーやOSのバージョンを記録しているものが存在します。
もしそれらが異なっているとロックがかかり、一度ロックがかかってしまうと最低でも数時間はログインできなくなってしまうほか、口座に不正なアクセスがあったと認識される可能性もあります。
もし個人利用のパソコンが使用できない場合でも、不正アクセスと疑われないためにできれば利用するネットワークは自宅のものにしましょう。
ネットワークにはIPアドレスというネット上の住所のようなものが割り当てられているため、できる限り亡くなった方が使用していた状態と同じ環境でアクセスすることを心がけてください。
また、事前にセキュリティソフトの利用期限が切れていないかも確認しましょう。
株式の所有者が亡くなってから数ヶ月以上経っている場合、使用していたパソコンのセキュリティソフトの有効期限が切れている可能性もあります。
無料でもよいので、事前にマルウェア対策を行うことを強く推奨いたします。
ウィルスなどに感染した状態でサイトにアクセスすると、現金の送金先を書き換えられる・個人情報の漏洩など、様々な被害が発生してしまう可能性があります。
株式の相続(遺産分割)
株式の相続は、
・株式を誰かがそのまま受け継ぐ(現物分割)
・株式を売却して、代金を相続人で分配する(換価分割)
・1人の相続人が株式を相続し、代償金を他の相続人が受け取る(代償分割)
などの方法で遺産分割が行われます。
一般的には、亡くなった方の管理しているアカウントを使用して所有株式を売却後に相続人の口座に送金します。
この場合、自分で株の売却を行うので、適切なタイミングで行うことができるというメリットがあります。
※事前にログインに必要なIDとパスワードを確認しておきましょう。
利用方法については、多くの証券会社の公式サイトにQ&A方式の案内が用意されていますので、難しくはないでしょう。どうしても分からない場合は、証券会社に問い合わせてみましょう。
株の売却後は、指定された個人の口座に送金して現金を相続することになります。
この際に、専門家に相談しておくと手続きをスムーズに完了することができます。
もしすでに専門家に依頼している場合には、連絡を密に取るとよいでしょう。
まだ依頼していないけど「難しそう」「相談できる人が欲しい」という方は、新潟相続協会にて無料相談を実施しておりますので、お気軽にご相談ください。
もし相続人がそのまま受け継ぐ場合には、相続人の証券口座を用意して振り替えを行う必要があります。
預金とは異なり、被相続人の口座自体の名義を変更するということができないため、必ず相続人名義の口座を別で用意しましょう。
株式の価値の算出方法
株式は金融財産のため、相続時はその価値を明確にする必要があります。このことを「評価」といい、評価額を基準として相続税を算出します。
上場株式を相続した場合、評価額の基準は「被相続人が亡くなった日の終値」となります。
そのうえで以下の4つの価格から最も低い価格を相続税の申告時の株価とします。
- 相続開始日の終値
- 課税時期の月の毎日の最終価格の平均額
- 課税時期の月の前月の毎日の最終価格の平均額
- 課税時期の月の前々月の毎日の最終価格の平均額
※詳しい算出方法は国税庁HPにて確認できます
株式の相続に時効はある?
株式の相続というより、相続税申告の時効は通常5年と定められています。計算の初日は「相続開始を知った日の翌日から10か月」となります。
しかし、相続税の申告と納付をしなければならないと知りながら故意に行わない場合は時効は7年になるので注意が必要です。
とはいえ、人が亡くなった際に役所に死亡届を提出すると税務署にも連絡がいく仕組みになっているため、時効までバレないと安易に考えるのは危険です。
また、株式の相続手続きを正しく行わないで放置していると、最終的には株式の権利がなくなるリスクも生じます。
株式取引を行っていない場合はとても難しく感じてしまい後回しにしてしまいがちですが、亡くなった方の大切な財産のためしっかりと手続きを行いましょう。
まとめ
故人の所持していた株式を確認するには
・証券会社へ問い合わせる
・通帳を確認する
・パソコンを確認する
・確定申告の控えを確認する
などの方法があります。
もし被相続人(亡くなった方)から株取引の詳細を知らされていない場合には、まずは郵便物や通帳、パソコンなどを確認しましょう。
所有株式が判明したら、名義変更や売却など適切な手続きを迅速に行うことをおすすめいたします。
株式の相続について、疑問点や不安な点がありましたらお気軽に新潟相続協会にお問い合わせ下さい。
初回無料相談をご用意しております。
亡くなった方の大切な財産ですので、知らずに時効になってなくなってしまったとならないように気をつけましょう。
※以上は本記事を作成時点の情報に基づいております。現在の内容と異なる場合があることをご容赦ください。
税理士への相続税・贈与のご相談はこちら

お気軽にご相談ください!
お約束1:感じの良い対応
お約束2:勧誘はいたしません
税理士・著書のご紹介(共著)

新潟相続協会 概要
新潟相続協会
(L&Bヨシダ税理士法人)
ご連絡先
◆新潟 相続オフィス
新潟県新潟市中央区女池4-18-18マクスウェル女池2F
☎025-383-8868
◆三条 相続オフィス
新潟県三条市東裏館2-14-15
☎0256-32-5002
対応地域
新潟県内全域対応
新潟県新潟市中央区、新潟市西区、新潟市東区、新潟市北区、新潟市江南区、新潟市西蒲区、新潟市南区、新潟市秋葉区、長岡市、三条市、見附市、加茂市、小千谷市、新発田市、村上市、柏崎市、上越市、胎内市、糸魚川市、弥彦村、燕市、五泉市、燕三条地域
その他県内全域対応












