相続は新潟の税理士に相談。相続税申告、相続節税対策、遺言、相続手続き承ります。相続税申告や手続きは税理士にご相談ください。
営業 時間 | 平日 9:00~17:30 ※夜間は要予約 |
|---|
相続はいつから開始する?
相続の開始日と相続手続きの期限について解説
家族が亡くなり、遺産がある場合、残された家族は遺産を相続し、相続に関連する手続きを行わなくてはなりません。では相続はいつから始まるのでしょうか?
相続の開始の基準は民法上で定められており、相続手続きもその開始日が基準となります。
ただ特殊な状況では相続の開始日がいつになるのか、迷うケースもあるかもしれません。このコラムでは、相続の開始と手続きの期限について解説します。
相続はいつから始まる?
遺産の相続はいつ始まるのでしょうか?
民法では882条に「相続は死亡によって開始する」と記載されています。「死亡によって開始」とは、財産を相続させる側、つまり「被相続人」が亡くなった時のことをいいます。多くの場合、被相続人が亡くなられた日から相続は開始します。
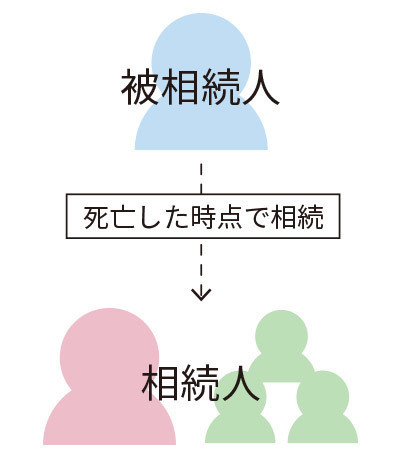
その他に相続については特別的な開始の要件などはなく、単純に「被相続人が死亡する=相続開始」となっています。被相続人が持っている権利や能力は、死亡と同時に相続が開始されます。
基本的に死亡については、医師の死亡診断書に書かれた時刻に従うこととなります。
相続する側(相続人)が相続に応じるか否かに関わらず、被相続人が亡くなることによって財産の相続はすぐに開始されます。死亡によって分割や相続人が相続の放棄をしてから開始されるのではなく、被相続人の死亡によってまず相続が開始し、分割や相続の放棄などの手続きをすると覚えておきましょう。
「相続開始日」の判定
前述のとおり、民法においては相続の開始日について、民法882条の「相続は死亡によって開始する」という記述があります。
それでは相続開始日はどのように判定するのか、もう少し詳しく見てみましょう。
亡くなられた日
一般的には、被相続人が亡くなられた日(死亡日)が相続開始日となります。
具体的に言うと、医学的に死亡が確認され、医師による死亡診断書の日付となる日です。
「死亡」以外で相続が発生するケース
被相続人が死亡したかどうかが不明な状況において、相続が発生するケースがあります。
例えば、下記のような状況が挙げられます。
- 行方不明になって数年が経過しており、今現在本人が生きているのか亡くなっているのかが家族にはわからない場合
- 事故や災害などに巻き込まれて生死不明の場合
このような場合、法律では「失踪宣告」と「認定死亡」という制度があります。
認定死亡の場合
認定死亡は、本人が死亡したとは思われるものの、災害などの結果として遺体が見つからない場合や、遺体の損傷などが著しく激しく本人と確認できない場合など、様々な事情により死亡したと認定することが難しいケースのために設けられた制度です。
警察などの官公署が死亡の認定を行い、死亡したものとして戸籍に記載された日が相続開始日とされます。
後にもし死亡していないことが判明した場合、認定死亡は取り消すことが可能です。
失踪宣告の場合
失踪宣告とは、現在生存が不明な人を、宣告を行うことにより法律上死亡したものとみなす制度です。
失踪宣告には行方不明となった原因に基づき、普通失踪と特別失踪があります。
普通失踪は通常時に行方不明である場合で、生死が7年以上明らかでないときに家庭裁判所の失踪宣言により認定されます。普通失踪のケースでは、行方不明時より7年間が経過した日が相続開始日とみなされます。失踪からの期間が7年以上経過している場合でも、相続開始日の考え方は変わりません。
自然災害などの危難により行方不明となった場合で、その危難が去ってから1年間生死が明らかでないときに家庭裁判所より認定されるのが特別失踪です。「危難が去った日」を亡くなられた日とし、その日が相続開始日となります。
認定死亡と失踪宣告の違い
認定死亡と失踪宣告の制度上の大きな違いは、認定する機関です。認定死亡は警察等の行政機関が死亡の報告を行い、管轄の市町村ですぐに認定を受けることが可能ですが、失踪宣告は家庭裁判所が判断を行います。そのため、認定死亡とは異なり、失踪宣告は取り消す場合には家庭裁判所にて再度審判が必要となります。
脳死の場合はどう判断する?
相続開始日は相続手続きの基準となる
相続手続きは原則として相続開始日を基準として期限が定められています。多くの手続きは「相続開始を知った日の翌日」が基準日となるため、その日を明確にすることで手続きの期限がいつになるのか判断できます。
相続手続きの期限が早く来る順に確認していきましょう。
※なお、以下の解説では「相続開始日」と「相続開始を知った日」は同じ日(被相続人が亡くなられた日)とします。
相続放棄または限定承認
事情により相続放棄を決断した場合は、相続開始の翌日から3ヶ月以内に申請する必要があります。申請をしない場合は相続放棄の効力は発生しません。相続放棄の申請は家庭裁判所に対して行います。
相続をする財産の中で、借金を返済し、財産が残った場合はそれを受け取り、逆に借金が残ってしまった場合には、財産の範囲内でのみ借金を引き継ぐという制度を「限定承認」といいます。限定承認の申請を行う期限も同じく3ヶ月以内となっています。
所得税の準確定申告
被相続人に確定申告の義務があった場合、相続人が代わりに「準確定申告」を行わなくてはなりません。準確定申告はその年の1月1日から、被相続人が亡くなられた日までの所得を対象として行います。その期限は相続開始の翌日から4ヶ月以内です。
相続税申告
相続税の申告期限は相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です。
遺留分侵害額請求
被相続人の遺言など、何らかの理由で遺留分が確保できない場合、相続人は遺留分に相当する財産を他の相続人に対して請求できる権利があり、このことを「遺留分侵害額請求」といいます。この権利の行使は相続開始を知った時から1年以内という期限が定められています。また相続の事実を知らなかった場合は、相続開始から10年以内が期限となります。
相続税の特例・軽減手続き
本来の申告期限までに遺産分割協議がまとまらない場合などは、まずは期限までに申告することを優先させるため、一旦法定相続分で申告したり、本来の相続財産より多めの評価額で申告・納税を行うケースがあります。
このような場合、相続税申告時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付することにより、申告期限後3年以内に相続税を軽減できる特例(小規模宅地等の特例や配偶者控除など)を適用できます。
「相続開始日」と「相続開始を知った日」はどう違う?
「相続開始を知った日」は相続関連の手続きについての説明でよく耳にする言葉ではないでしょうか。では、「相続開始日」と「相続開始を知った日」に違いはあるのかどうかを考えてみましょう。
一般的には、「相続開始日」は被相続人が亡くなられた日であり、多くの場合、相続人はその日に相続開始を知ることになりますので、「相続開始を知った日」は同じ日となることが殆どといえます。
しかし亡くなられた事実を相続人が知らなかったという場合もあります。例えば、相続人である子が離婚のため被相続人の親と疎遠だった場合や、海外など遠方におり連絡がしばらくつかなかった場合などです。
そのようなケースでは、相続開始を知った日は被相続人が亡くなられた日、つまり相続開始日とは異なります。相続手続きの基準となる日は「相続開始を知った日」の翌日からとなり、亡くなられた日の翌日からではないことに注意しましょう。
一定期間が経過してから相続人となった場合
まとめ
今回のコラムでは、相続がいつから開始されるのか、相続開始日と相続開始を知った日の違いなどについて解説しました。基本的には被相続人が亡くなった時点で相続が始まり、相続開始後に相続関連の手続きを行うことになります。相続手続きの期限は相続開始日(相続開始を知った日)が基準となりますので、期限内に進められるよう計画的に準備していきましょう。
ご不明な点があれば、相続税に強い新潟の税理士にご相談ください。当社では初回のご相談を無料で受け付けております!申告期限が近い場合も、まずはお気軽にご相談ください。
※以上は本記事を作成時点の情報に基づいております。現在の内容と異なる場合があることをご容赦ください。
税理士への相続税・贈与のご相談はこちら

お気軽にご相談ください!
お約束1:感じの良い対応
お約束2:勧誘はいたしません
税理士・著書のご紹介(共著)

新潟相続協会 概要
新潟相続協会
(L&Bヨシダ税理士法人)
ご連絡先
◆新潟 相続オフィス
新潟県新潟市中央区女池4-18-18マクスウェル女池2F
☎025-383-8868
◆三条 相続オフィス
新潟県三条市東裏館2-14-15
☎0256-32-5002
対応地域
新潟県内全域対応
新潟県新潟市中央区、新潟市西区、新潟市東区、新潟市北区、新潟市江南区、新潟市西蒲区、新潟市南区、新潟市秋葉区、長岡市、三条市、見附市、加茂市、小千谷市、新発田市、村上市、柏崎市、上越市、胎内市、糸魚川市、弥彦村、燕市、五泉市、燕三条地域
その他県内全域対応












